介護の現場やご家庭で、認知症の高齢者と接するとき、声掛けの仕方ひとつで安心感や信頼関係が大きく変わります。
逆に、何気ない一言が混乱や不安を招いてしまうことも。
この記事では、介護職の方やご家族に向けて、「認知症高齢者への声掛けの注意点」を具体例とともに解説します。
1.ゆっくり・はっきり・短く話す
認知症の方は、情報処理に時間がかかることがあります。
早口や長い説明は混乱の原因に。
- 1文1情報を意識する
- 簡単な言葉を使う
- 間を置きながら話す
例:
×「ご飯を食べたら着替えて歯磨きして散歩に行きましょう」
〇「ご飯を食べましょう」「次は着替えましょう」
2.名前を呼び、目線を合わせてから話す
いきなり話しかけると、びっくりされることがあります。
まずは名前を呼び、目線を合わせて存在を伝えることから。
- 正面から近づく
- 名前を呼んでから話す
- 目線を同じ高さに合わせる
3.否定よりも公定で伝える
否定形は不安や混乱を招きやすいため、肯定形で案内しましょう。
- ×「立たないでください」
- ○「ここに座っていてください」
4. 質問は具体的に、選択肢は2つまで
抽象的な質問や選択肢が多すぎると答えにくくなります。
- ×「どうしますか?」
- ○「お茶とお水、どちらがいいですか?」
5. 間違いを強く訂正しない
認知症の方が日付や出来事を間違えても、頭ごなしに否定すると混乱します。
会話の流れを崩さずにやんわりと正しい情報に置き換えるのがポイント。
6. 感情を受け止めて共感する
内容よりも感情への共感が大切です。
- 「怖い」と言われたら理由よりも安心感を与える
- 「それは心配でしたね」と受け止める言葉を添える
7. 環境を整えて声掛けする
テレビや人の出入りなど、雑音が多い環境は集中しづらくなります。
静かで落ち着いた場所で声掛けしましょう。
まとめ|「言葉」より「安心感」を届ける声掛けを
認知症の高齢者にとって、会話は情報よりも安心感のやり取りです。
ゆっくり・やさしく・肯定的に接することで、介護の時間がもっと穏やかで温かいものになります。
おすすめ書籍:
認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズ | 佐藤 眞一, 島影 真奈美 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで佐藤 眞一, 島影 真奈美の認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズ。アマゾンならポイント還元本が多数。佐藤 眞一, 島影 真奈美作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズもアマゾン配送商品なら通常...
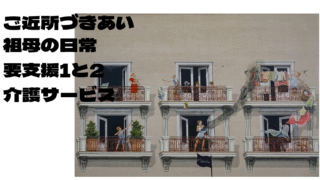
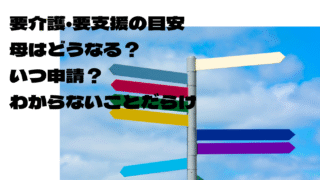

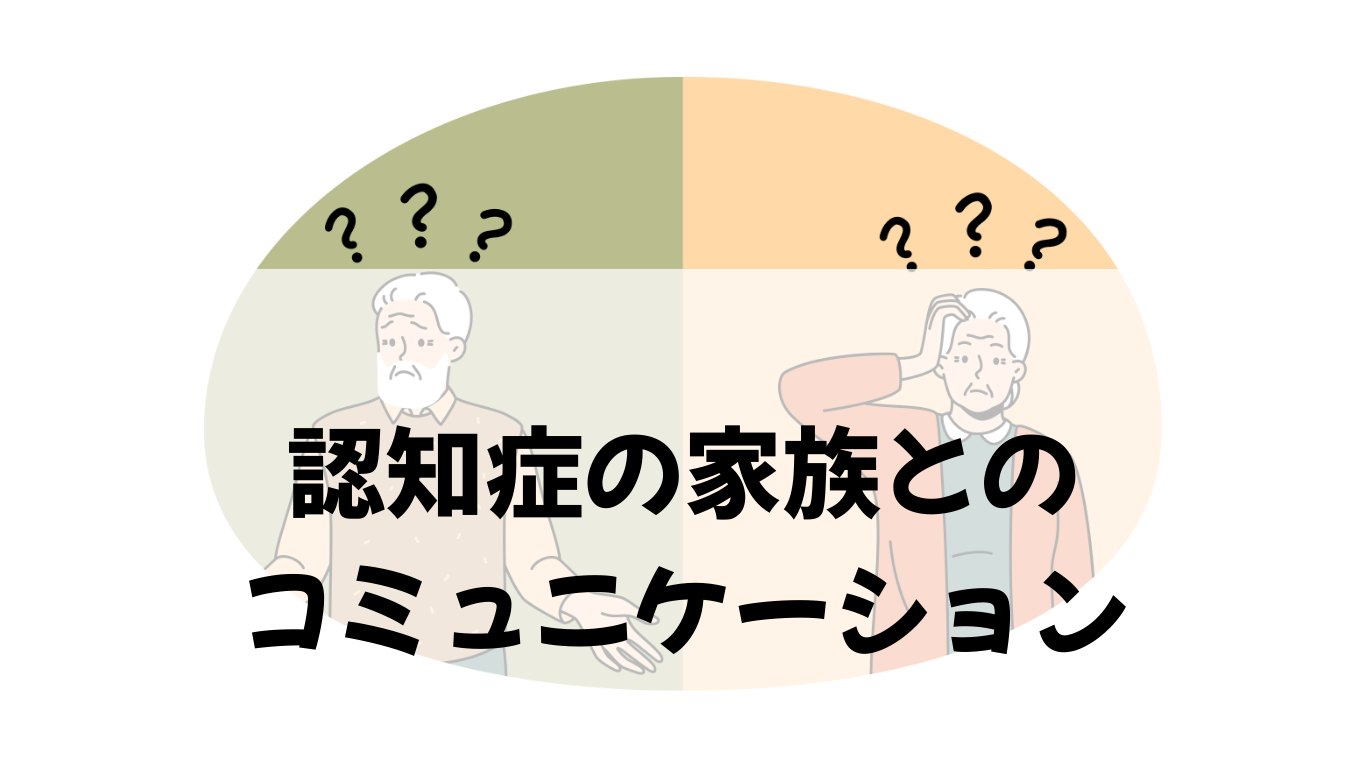
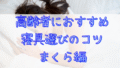
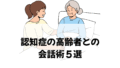
コメント