認知症ケアの現場では、「何を話すか」よりも「どう話すか」が大切です。
正しい会話の工夫を知ることで、介護する側もされる側も安心できる時間が増えます。
ここでは、介護職やご家族が今日から実践できる5つの会話術をご紹介します。
1. バリデーション(感情の受け止め)
認知症の方が事実と異なることを話しても、正そうとするより感情を理解することが優先です。
「怖い」と言われたら理由を探る前に「怖かったんですね」と共感を示しましょう。
ポイント
- 否定しない
- 相手の感情に寄り添う
- 共感の言葉+安心感を与える一言を添える
2. リミニッセンス(回想法)
昔の思い出や経験を話題にして記憶を刺激します。
古い写真、当時の音楽や香りは会話のきっかけになります。
例
- 「この写真、○○さんが若い頃の○○ですね」
- 季節行事や昔の仕事の話を聞く
3. 非言語コミュニケーション
言葉が通じにくくなっても、表情・しぐさ・声のトーンはしっかり届きます。
やさしい笑顔やゆっくりした動きは、安心感を与えます。
ポイント
- 穏やかな表情を保つ
- 動作はゆっくり大きめに
- 触れるときは声をかけてから
4. 環境調整
コミュニケーションは静かで落ち着いた環境で。
テレビの音や人の出入りを減らすだけで、集中して会話ができます。
5. シンプルな言葉と短い文章
一度に複数の情報を伝えないようにします。
「ご飯を食べましょう」→○
「ご飯を食べて、着替えて、歯磨きして」→×
まとめ
認知症ケアにおける会話の目的は、情報伝達だけでなく安心感の共有です。
感情を受け止め、相手の世界を尊重しながら接することで、介護の時間がより温かくなります。
おすすめ書籍:
認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズ | 佐藤 眞一, 島影 真奈美 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで佐藤 眞一, 島影 真奈美の認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズ。アマゾンならポイント還元本が多数。佐藤 眞一, 島影 真奈美作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また認知症心理学の専門家が教える 認知症の人にラクに伝わる言いかえフレーズもアマゾン配送商品なら通常...
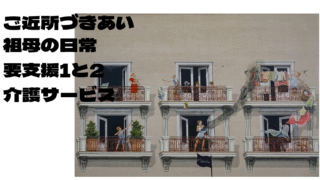
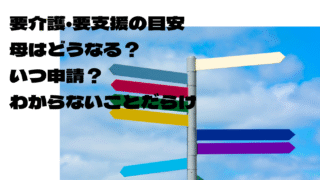


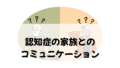
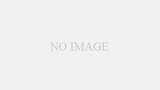
コメント