介護施設に持っていく服に悩んでいませんか?
自分が着る服は簡単に選べますが、着る人の相手のことを考えると決めきれないことがあります。
ましてやその相手が介護を必要としている人物だと、余計に悩んだりします。
祖母の服選びでしっかり悩んだ経験をお伝えしていきますので、良かったら参考にされてください。
服選びのコツ5選+1
- 乾燥機にかけられること
- 前開きであること
- 丈が長すぎないこと
- 着心地が良く、ゆとりがあること
- 名前が書けること
- 靴はどうする?
祖母はまだ施設には入所していませんが、すでに介護認定の通知は来ているので利用しているサービスがあります。
そこで準備してほしいと言われたのが着替え。
いずれは入所を視野に入れ、持っていく着替えで気をつけたことをまとめました。

【ハナサンテラス】護下着 女性 前開き 2枚組 3分袖 ワンタッチ テープ 介護用肌着 大人用 綿100% (ピーチ, S)
1.乾燥機にかけられること

洗濯したらそれで終わりではありませんよね。
干さないといけないんです。
乾燥機を使ったことがある人はあの便利さは、あえて言わなくても大丈夫ですかね(笑)
私は子供の洗濯物で何度助けられたか分かりません。
特に梅雨時期と冬。
次から次へと出てくる洗濯物。でも乾かない現場。
乾いてない現場に新たな洗濯物で湿地帯の出来上がり。
私の場合は湿地帯を防ぐことに乾燥機のありがたみを感じていましたが、
祖母に乾燥機を必要としている理由は”母の負担を減らしたい”です。
母はまだ負担と感じていないと言いますが、これから祖母の様子がどうなるか分かりません。
洗濯の回数が増える可能性だってある。
「あ、ほとんど洗濯してるから乾いた服がこれだけしかないわ」
なんてことが防げるんじゃないでしょうか。
それに施設での洗濯は乾燥機を使うことが多いと聞きます。
生地が縮むことが十分に考えられるので、これから服を買い足そうというなら乾燥機に対応した服がいいですよね。
乾燥機に入れても縮みにくい素材
合成繊維
- ポリエステル: 最も縮みにくい素材の一つです。形状安定性に優れ、速乾性もあります。
- ナイロン: ポリエステルと同様に、縮みにくく丈夫な素材です。
- アクリル: ウールに似た風合いを持ちながら、縮みにくい性質があります。
- ポリウレタン(スパンデックス、ライクラ): 伸縮性に優れ、他の繊維と混紡されることが多いですが、それ自体も比較的縮みにくいです。ただし、高温に弱いため、乾燥機の温度設定には注意が必要です。
加工された天然繊維
- 防縮加工された綿 (Preshrunk cotton / Sanforized cotton): 綿は本来縮みやすい素材ですが、防縮加工が施されているものは、乾燥機に入れても縮みにくくなっています。購入時にタグを確認すると「Preshrunk」や「Sanforized」といった表記がある場合があります。
- 加工されたウール(ウォッシャブルウール): ウールは非常に縮みやすい素材ですが、特殊な加工が施されたウォッシャブルウールは、家庭での洗濯や乾燥機にも対応できるようになっています。
乾燥機を使用する際のポイント
素材に関わらず、乾燥機を使用する際は以下の点に注意すると、衣類の縮みを最小限に抑えられます。
- 洗濯表示を確認する: これが最も重要です。乾燥機使用の可否や、設定温度などが記載されています。
- 低温設定にする: 高温は繊維を収縮させやすいので、可能な限り低温または「デリケート」「弱」などの設定を選びましょう。
- 短時間で乾燥させる: 必要以上に乾燥させないように注意し、生乾きの状態で取り出して自然乾燥させるのも有効です。
- 風合いを重視する衣類は避ける: 大切な衣類や縮ませたくない衣類は、できるだけ自然乾燥させるのが最も安全です。
これらの情報を参考に、お持ちの衣類の素材と洗濯表示を確認して、乾燥機を上手に活用してください。
2.前開きであること

- 着脱が容易で介助者の負担を軽減する:頭からかぶるタイプの服に比べて腕や体を大きく動かす必要がないので介護される側は負担が少なく、介助者は時間と労力を削減できる。
- 身体の状態に合わせた調整がしやすい:診察や処置が必要な時、すべて脱がせる必要がなくなることと、体温調節がしやすい。
- 自立支援につながり、羞恥心を軽減する:ボタンを留める・ファスナーの上げ下げなど、自分で出来る動作があればリハビリの一環として取り組め、残存機能の維持ができる。
セラピストをしていたときの経験ですが、お客様に着替えとしてTシャツを準備していました。
ですが、関節が硬いとのことでお着替えが難しく、お帰りの際のコートを羽織る動作も難しそうにされていた方がいらっしゃいました。
コートさえ羽織ることが難しいのに頭からすぽっと着るようなタイプの服は袖を通すのがめちゃくちゃ大変ですし、脱ぐ時も大変です。
祖母の服選びで改めて気づいたことがあります。
いつもエプロンをつけているので気づきにくかったけど、祖母の持っている服は前開きが多いかも。
祖母は「健康だけが取り柄」+頑固な性格でしたから身体に不調があっても教えてくれません。
”本当に不調がないから言う必要がなかった”という可能性はありますが、自分からSOSが言いにくい高齢者なら持ち物に色々ヒントがあるかもしれませんね。
3.丈が長すぎないこと

着用する服は、動きやすく、安全性が確保できるような、適切な丈のものが推奨されます。具体的には、足首が隠れる程度で、床に引きずらないくらいの丈が目安とされます。
- 転倒のリスクを軽減するため:介護の現場において、利用者さんを支える際に服の裾に引っかかったり、些細なことがケガにつながるから。
- 車いすやその他の機器への巻き込みを防ぐため:丈の長い服が車いすの車輪やフットレストに巻き込まれて転倒の可能性があるから。
- 動作の妨げにならないようにするため:利用者さんを支えたり、体位変換を行うなど、様々な動きがあります。丈が長いと踏まないように、引っかからないようにと、介助に必要な動作に制限をかけないようにするため。
- 衛生面への配慮:床に引きずるような丈は衛生面上よくありません。感染症のリスクを避けるためにも、清潔を保ちやすい丈の服が望ましいです。
4.着心地が良く、ゆとりがあること

介護者が着用する服は、丈が長すぎるだけでなく、逆にピッタリすぎる(タイトすぎる)サイズも避けた方が良いとされています。
- 着脱のしやすさと身体への負担軽減:ぴったりする服では動きに制限がかかるため、身体への負担がとストレスの原因になります。
- 床ずれや皮膚トラブルの予防:締め付け間のある服は血行不良で床ずれの原因になることがあります。通気性の良い服が皮膚トラブルも防げます。
- 体温調節のしやすさ:ゆとりのある服は体温が上がりすぎることを防ぎます。季節に合わせて着脱しやすい服は体温調節を助けます。
- 心理的な快適さと自尊心の維持:着心地の良い服は安心感とリラックス効果があります。スムーズに着替えられることで羞恥心を軽減し、自尊心を保つことにつながります。
着心地の良い服は天然素材の綿やシルクですが乾燥機に対応できるかが重要です。
着心地が良い+乾燥機に耐える素材
”乾燥機に耐える” ”縮みにくい” ”シワになりにくい”
という複合的な要素を考えるなら洗濯表示は注意してくださいね。
- ポリエステル混紡素材(特に綿ポリ):綿の肌触りの良さと吸湿性あり。ポリエステルは高温に弱いため、低温設定で乾燥させるのがおすすめ。
- ポリエステル100%(特に高機能素材):汗をかいてもサラサラとした感触を保つ「ドライタッチ」素材。高温での長時間乾燥はシワや繊維の傷みの原因になることがあるため、低温で短時間の乾燥がおすすめ。
- 防縮加工された綿(プレシュランクコットンなど):綿本来の柔らかく、吸湿性に優れた着心地は抜群。「防縮加工(Preshrunk加工)」が施されている綿は、そのリスクが大幅に低減されています。購入時はタグはしっかりチェックしてくださいね。
- ウォッシャブルウール / 防縮加工ウール:ウール特有の保温性と吸湿性あり。チクチク感はなく、非常に柔らかい素材。「ウォッシャブル」や「防縮加工」と表示されているウールは、家庭での洗濯・乾燥に対応できるよう特殊加工が施されています。タグはしっかりチェックしてくださいね。
乾燥機を使うなら避けた方が良い素材
- レーヨン、モダール、テンセル(リヨセル):水に濡れると強度が著しく低下し、乾燥機にかけると大きく縮んだり、ゴワゴワになったりする可能性が高いです。
- ポリウレタン(スパンデックス、ライクラ):伸縮性素材で、他の繊維と混紡されていることが多いですが、熱に非常に弱いです。乾燥機にかけると生地が傷んだりすることがあります。
- 麻(リネン):綿と同様に縮みやすく、シワになりやすい特性があります。
最も確実なのは、製品についている洗濯表示タグを確認することです。
どんな生地でも乾燥機にかけると少なからずダメージはあります。
自宅では低温、短時間でやっていきましょう。
5.名前が書けること

- 紛失防止:多数の利用者さんと共同生活を送る場では、洗濯もまとめて行われることも。洗濯後や、他の場所へ移動した際に、誰の服かすぐに識別できます。
- 誤着用の防止:名前が確認できることで、他の方の服を誤って着用してしまうことを防げます。
- 個別管理のしやすさ:衣類だけでなく、持ち物全般に言えることですが、介護現場では利用者さん一人ひとりの持ち物を適切に管理する必要があります。名前が明記されていれば、職員が服を整理したり、渡したりする際にスムーズに作業が進みます。
- 清潔保持:自分の衣類を常に清潔に保つことは、利用者さんの尊厳を守る上でも重要です。名前があることで、定期的な交換や洗濯が確実に行われるようになります。
名前を記入する際のポイント
- 目立つ場所:服の裏側やタグなど、目立つ場所に記入しましょう。
- 消えにくい方法:油性の布用ペン、アイロン接着タイプの名前シール、縫い付けるタイプのネームタグ。洗濯しても消えない工夫が大事です。
- フルネームで:同姓の方がいる可能性を考慮し、フルネームで記入するのが確実です。
服に名前を記入する手間はかかりますが、その後の管理や紛失防止を考えると、非常に大切な準備です。
6.靴はどうする?
多くの施設はレクリエーション、リフレッシュのため外出の機会を設けています。
お出かけする際の靴選びは、安全性と快適性が最も重要です。
利用者さんの身体状況や、車椅子利用の有無、お出かけの内容(散歩、買い物、通院など)によって適切な靴は変わってきますが、一般的に以下の点がポイントになります。
- 滑りにくい靴底
- 足にしっかりフィットし、脱げにくい
- クッション性がある
- 着脱が簡単
高齢者におすすめの靴の比較を作っています。
良かったらコチラも参考にされてください。
| 項目 |
|  |
|---|---|---|
| 脱ぎ履きのしやすさ | ◎(手を使わず履ける) | 〇(しゃがむ必要あり) 履き口が広いので履きやすい |
| 靴の重さ | 250g以下 | 250g以下 |
| フィット感 | 足のむくみにも対応 | ストレッチ素材 クッション性のあるインソール 偏平足・外反母趾に対応 |
| 滑りにくさ | ◎(滑りにくい底) | 製品による |
| デザイン | シンプルで日常使いに | 機能性シューズとは思えない 華やかなデザイン |
関連記事:高齢者におすすめの靴
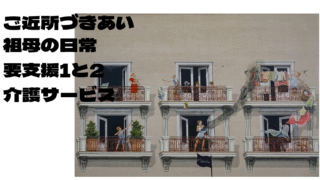
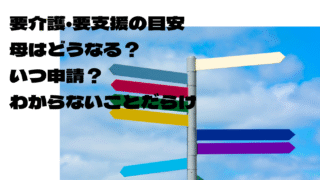

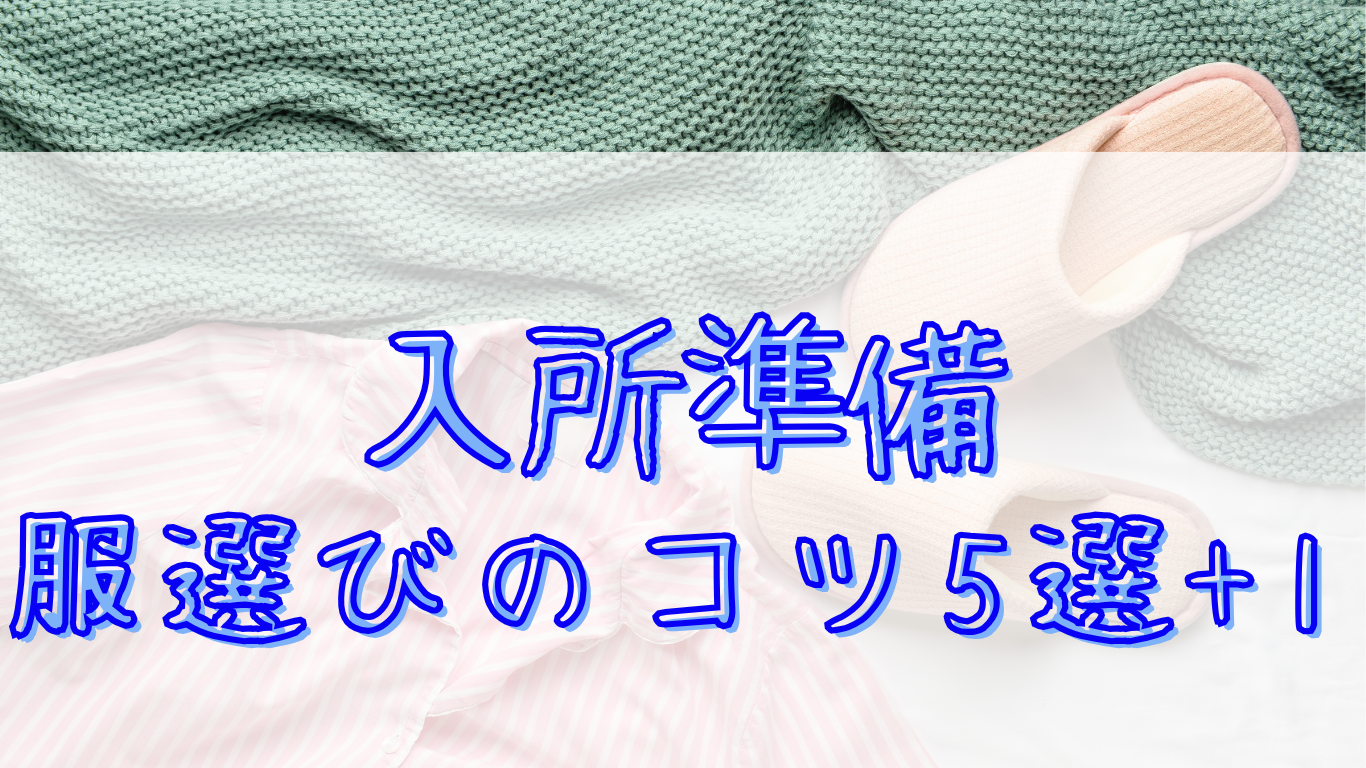
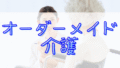
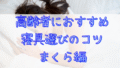
コメント